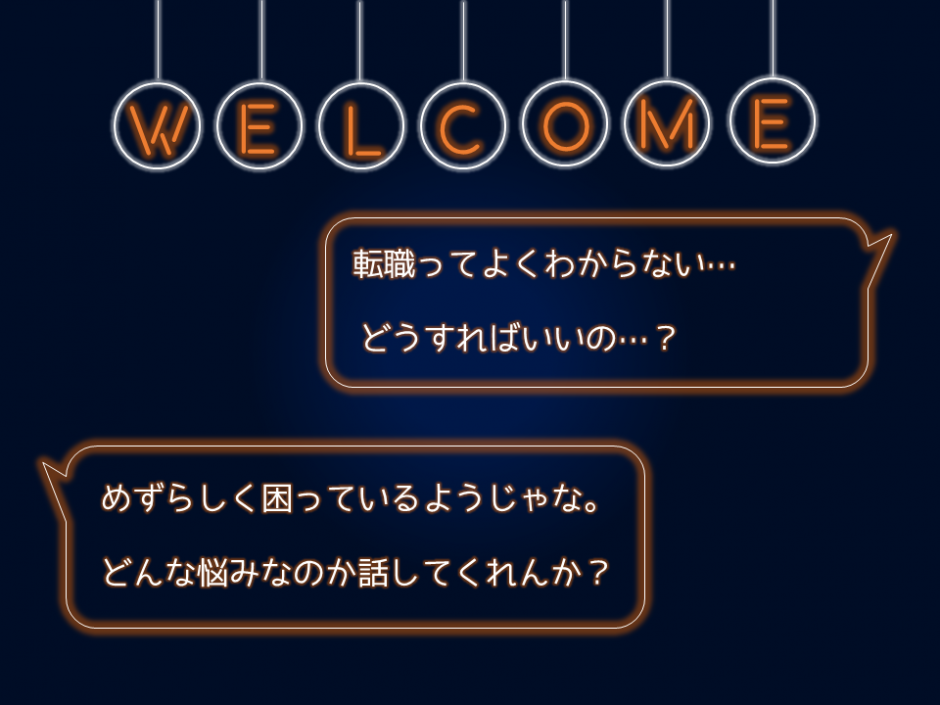今回はNHKディレクター、倉崎憲さんのIKIKATA。
これまで49か国を旅してきたという倉崎さん。ラオスでの小学校建設活動に携わり、世界一周を個人協賛で実行するなど世界を広く見てきた彼は、どのような経緯でディレクターとして仕事をしているのでしょうか。
静かに語る言葉の一つ一つに「熱い思い」がある倉崎さんの生き方からは、私たちがどのような思いをもって日々生きるべきか、そして仕事をしていくべきかを学ぶことができます。
具体的な業務
今、山形ではドキュメンタリー番組、スポーツや祭りなどの中継から地域発ドラマまで色々やっていて。メインは「番組を作ること」。企画を考え、ネタを探し、出演者が必要ならキャスティングして、ロケをして、編集して音楽をつけたり、企画から番組OA後まですべてに関わる、ディレクター業務をやっています。
—企画を考えるところから担当されているのですね。
Eテレ「人生デザイン U-29」という、29歳以下の若者に密着する番組があって、色々な職種の方を毎週取り上げているのですが、僕は山形の田舎町のグラフィックデザイナーに密着させていただきました。人探し、取材をして、編集まで行っています。
ディレクターは番組の始まりから最後まで責任を持ちます。
—映像に音楽をつけるという行程にも携わるのですか?
音楽をつけてくれる音響効果さんと話しながら、どのシーンに音楽をつけるのか、どのカットからどのような音楽、または効果音をつけるのかとか、そういった最終的な判断はディレクターの仕事になりますね。
—「放送の枠」つまり番組を作る数は、あらかじめ決められているのでしょうか?
決められている番組の枠もありますけども、ディレクターの仕事は「提案」をするところから始まるんです。全国どこにいたとしても、「伝えるべきもの」がある。それは人の生き様であったり、社会問題であったり、文化であったり、活動であったり、対象は様々ですが、自分が世の中に伝えたいもの、伝えるべきことをとことん取材していって。
そのあと、提案表に「なぜ今これを取り上げるのかという狙い」や「構成案」を書きプレゼンする。それが通って初めて撮影ができます。ですから、無意識のうちに365日アンテナを張っていますね。
—以前は東京でドラマを担当していたとのことでしたが、働き方に違いはありますか?
山形では、ドキュメンタリー番組や「花笠まつり」「Jリーグ」中継など、地方局でしかできないことをやりまくっている、という感じですね。
でも、ドラマとドキュメンタリーには共通するものがあって。ドラマはフィクションだけど、「リアリティー」が求められていて、根底にあるものはドキュメンタリーと一緒なんです。実在するものをいかに描けるかというところが大前提なんですね、「取材第一」。
たとえば、ドラマの登場人物にリアリティーがないと、「実在する人」として立ち上がってこないんですよ。
取材は基本マイカーで行うんですが、3年で4万キロの移動距離になるほど、北から南へ走り回っています。ひたすら様々な人に会って話を聞いて景色を見て取材しまくって。それがドラマにも活きてくるというか。
結局、フィクションもノンフィクションも「リアル」がないと人は見ないですから。共感も感動もしないですし。「リアル」というか真実というか、実際に「生きている」ものを日々求めている、みたいな感じですね。
—素人目線だと、ドラマ撮影には俳優さんが脚本に沿って作っていく、というイメージがあります。フィクションであっても、取材を通してノンフィクションに近づかせていくことを考えているということでしょうか。
そうですね。
去年、ドラマを作ったんですよ。「私の青おに」というオール山形ロケのドラマです。「泣いた赤おに」という山形県高畠町で作られた名作童話を題材・モチーフにして、赤おにと青おにの「その後」を描いた話を作ったんです。
童話の中では、「赤おにの元から青おにが去っていって、本当の友情を失ったことに気づいた赤おにが、青おにが残した貼り紙を読んで号泣するというラスト」で終わる話なんです。
昔、実家で読み聞かせてもらっていたし、小学校の道徳の教科書にも載っていた話だったので知っていたんですが、山形に来てから20年ぶりに読んだら、子どものころに読んだときには感じなかった「切なさ」を感じて。「赤おにと青おにってこの後どうなったんだろう?」「この後は再会できたんだろうか?」とか、そういった素朴な疑問が浮かび上がってきたときに、「これをドラマにすればいいのではないか?」と思ったんです。
現代劇として、赤おにと青おにを「20代後半の、自分の人生や仕事に対して色々思うところのある女性」に置き換えて、その後の物語を作れないかな、と。そうした時に、さっきの話に結びつくことですが、モチーフを徹底的にリサーチするんです。
実際に現代劇として「赤おに」役は東京の出版社で働いている編集者、「青おに」役は、山形の片田舎でぶどう農家の娘として働いているという設定にしたんですが、そのときに実際の出版編集者やブドウ農園を取材しまして。「どういう服装をしているのか?」「どんな作業をしているのか?」ということも全部含めて取材しました。
役者さんにはもちろん台本があって、ト書きもあるんですが、セリフやト書きの「行間」が凄く面白くて。監督や役者さんが、台本の行間をどう読み解くかというところですね。
役者さんは作り手の想像を上回るような仕事をしてくれて、山形の風土もそれを押ししてくれて、素晴らしいものができあがって。
僕はいわゆる「絶対にそんな人はいないよね」という芝居をする「いわゆる芝居!」が大嫌いで。僕はそういうものを一切排除したいというか。
役者さんは”芝居”をするけれども、なるべく素でいてもらう。役になりきるというか。そのために撮影前から役者さんとめちゃくちゃ話をするし、方言を使う場合はその練習も徹底的にしてもらうし。ぶどう農家役の役者さんには、時間の許す限りぶどう農家の人と話してもらうし、作業を一緒にしてもらう。「なるべく”その役”であってもらう」「”その役”で生きてもらう」その瞬間に一番強いものが撮れるんです。
ドラマも「ドキュメンタリーのように撮りたい」と思っていますね。
—編集が終わり最終確認した番組が実際に放送されたとき、初めて分かることはありますか?
世間の反応です。「世の中の人がどういう風に観てくれるんだろうな」と、Twitterなんかもめっちゃ検索しますし(笑)
—番組を観た世の中の人々の反応をしっかり見る。
たとえば、自分が番組で気になっていたところが、いい意味で受け止めてもらえることもありますし、逆に自信満々で繋いだ部分がなかなか受け入れてもらえなかったり…ということがあるので。価値観は年代や性別によって全然違うというところが分かる仕事ですね。時には数千万人、数百万人に届けられるテレビだからこそ面白い。

倉崎憲(くらさきけん)京都府出身の28歳。同志社大学卒業後、2011年NHK入局。ドラマ番組部に配属され、大河ドラマ「平清盛」などの助監督を経て、初演出したラジオドラマ「世界から猫が消えたなら」(主演:妻夫木聡)でギャラクシー賞奨励賞、イタリア賞ファイナリスト。他の演出作品に、救急車を舞台とした小説をラジオドラマ化した「迷走」(主演:市原隼人)など。2015年、ドラマ「私の青おに」でテレビドラマ初演出。旅と写真を愛し今まで世界一周を含む49カ国を旅する。書籍「僕たちは世界を変えることができない。」(星雲社)写真担当。南アフリカフォトコンテスト最優秀賞受賞。
今の仕事についた経緯・キッカケ
旅が大好きで、今まで49か国周ってきたんです。その中で初めて行った国がラオスという東南アジアの国。そこで「小学校を建てよう」という活動をしていました。
カンボジアで我々と同じような活動をしている団体が関東にいまして、その団体の方から「mixi」で連絡がきて、「国は違うけど似たような思いでやっている」「子どもたちに教育の機会を作りたい」という連絡が来たんです。
そこで、我々の活動を赤裸々な本にして出そうと。カンボジアにも行きましたし、カメラをどこにいくのでも持っていましたから、現地で写真を撮っていて。それが、『僕たちは世界を変えることができない』という本になりました。
2011年に向井理さん主演で映画化もされて、撮影現場にも行かせて頂きました。現場を見てすごく感動して。それまではドラマや映画はあまり見ていなくて、ちょっと斜に構えていたんですけど。「どうせ作り物だろ」みたいな(笑)
監督は深作健太さんだったんですが、(深作さんの)台本が凄くクシャクシャだったんですよ。僕らが学生時代、テスト勉強していて教科書を何回も使っているうちにクシャクシャになる、そんな感じでした。
数百回、数千回とこの台本と向き合いながらどういう演出をしようか、ということを考えていたんだろうなと分かる状態で。主演の向井さんは「ウルルン滞在記」でカンボジアにも言った経験がおありで、上手く感情移入できていて。
その様子を見て「すごいな」と思いましたね。セリフやト書きの「行間」を、台本を読んでいるだけで立ちあげていって。自分たちの活動、なんてこともない大学生の活動が、こうやって映画にされていくと。
世間からの反響は大きくて、映像の力ってすごいなと。自分たちの活動を知ってもらうだけだと誰にも伝わらないのに、映像化してもらえることで多くの人に観ていただけて、そこからまた新しいアクションが生まれたり、感情が生まれたり…というサイクルを肌で感じました。
そこで、「ドラマ、映画を撮りたい」「ドラマの監督になりたい」と感じ始めたんです。
NHKに入るまでにはそれ以外にも色々な理由があって。色々な国で映画の撮影現場に行かせてもらって。パリとかロスとか。撮影スタッフもキャストも多国籍な現場を見たんですけど、パリで映画の撮影現場を見たときに、様々な国籍のスタッフがいる中で一人だけ日本人の方がいまして。僕の中で「サムライ」に映って、凄くかっこよかったんです。
あと、スタッフの方々が「ワンカット」にすごく時間をかけるんです。2~3秒のシーンに2時間とか平気でかける。
それぞれの分野のプロフェッショナル達が、そのワンカットのために最善を尽くしている。「狂気の現場」というか、混とんとした感じ。それを見ているとめっちゃアドレナリンが出てくる。かつ、撮影したものを多くの人に観てもらえる。こんな幸せな仕事はないんじゃないかと。
撮影したものを観て、ちょっとでも行動を起こせたり、素敵な人や場所、景色を伝えることが出来るのは凄く幸せなことだと思いました。
ざっくりいうと、そういった思いでNHKに進んだという感じですね。
東京では3つのドラマを担当したですが、そのうちの一つに奄美大島と、加計呂麻島が舞台のドラマで「ロケーションマネージャー」を務めたことがありました。ロケーションマネージャーというのは、たとえばスタッフやキャストの宿の確保、ロケ地へのアクセス、ロケ地の交渉、現地のキャストのキャスティングなどといったもろもろを占めてやっていく役割です。
たいていは全国どこでも「フィルムコミッション」というのが存在していて、たとえばおすすめの場所を教えてくれたり、地元のエキストラを集めてくれたりするんです。でも、加計呂麻島や奄美大島には、フィルムコミッションは存在しない。なので、自分たちで開拓していかなければならず、島民の皆さんに協力してもらわなければならなかった。
撮影の数か月前から現地に行って島を回りまくって、島の方々と腹を割って話して。一方通行ではなくて、「加計呂麻島、奄美大島でドラマを一緒に作りませんか?」という双方向のコミュニケーションで進めていく。
奄美大島や加計呂麻島って、ハブが出そうなところがあるじゃないですか。起こりうる可能性として、キャストやスタッフが噛まれる危険があるので、出そうなところで撮影をするときには、島の病院の看護師さんに「来てください」とお願いしましたね。
また、そもそも起きる前に処置をしなくてはいけないので、「ハブ獲り名人」に来てもらう。その名人が誰かと言ったら、島のタクシーの運転手なんですよ。トランクにシュッとする「アレ」を持っているんですよね(笑) 島にはそもそも、「ハブ獲り名人」なんて存在しないんですけど、来ていただいて。
そういうことに関するマニュアルとかって、何もないじゃないですか。別にハブ獲り名人に頼む必要もないんですけど、すべてを想定してイチバンいい方法を採って、現場が撮影に集中できるようにしていましたね。
撮影をする地域には、自分が歩いて行かないとわからないし、その地域に入ったからといって「入り切れていない」こともあります。何度も何度も、時間の許す限り走り回る、歩き回るということが何よりも大事です。島の皆さんにも、よそ者ではなくて「一緒にドラマを作る仲間」という目で見てもらうことが大切で。
「何かを実現する」って、人ひとりの行動だったり許可だったりすることもあるから、何かを実現するためには、だれとどんな話をするのかということを客観的に見ることが大事だなということは、島ロケで学びましたね。
![IKIKATA [イキカタ]](http://pras.wp-x.jp/wp-content/uploads/2017/10/ikikata-logo.png)